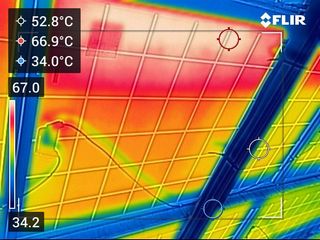| 皆様こんにちは。塚本空調設備です。 前回の投稿からすぐに出すつもりが、気がつけば年末になってしまいました。 どうやら2024年最後の投稿です。よろしくお願いいたします。 前回の続きとなりますが、 まだ見ていない方はこちらを御覧頂ければ話が繋がります。 ☆太陽光発電の定期報告 ちゃんと報告していますか? (その1) https://tsukamoto-re.com/658/ |
「委託に係る事項」って何?
| 原文をそのまま転記しますが、最初に言っておきますけど「内容を理解しようとして読まなくて大丈夫」ですから。 *********************************************************** 委託に係る事項 2025年4月以降は必ず記載すること。 なお、定期報告の内容等を端緒として、認定事業者が委託先に対する監督義務を適切に履行していないおそれが発覚した場合には、必要に応じて報告徴収・立入検査を行い、委託契約書の原本や監督義務の実情を詳細に把握したうえで、監督義務の不履行が確認されたときは、指導・認定取消しといった厳格な対応を行う。 報告義務の対象となる委託は、「委託の種類」欄に記載した業務に係る委託であって、認定事業者が直接委託するものに限る。 ただし、再エネ特措法第10条の3第2項に基づく監督義務は、再エネ発電事業の実施に係る行為全般について、再委託先にも係るものであることに留意すること。(詳細については、「再生可能エネルギー発電事業に係る業務の委託について(運用指針)」を参照すること。) また、当該報告の対象期間(設置費用報告の場合にあっては、運転開始までの期間)に契約期間が属するものを対象とする。 報告対象となる委託契約ごとに記載すること。複数の委託がある場合は、枠を追加すること。 *********************************************************** という事で、ここに至る経緯(背景)が分かりませんと理解しにくいと思います。 とは言いつつも、赤文字で強調した部分には「認定取り消し」と書いてありますので、知らんふりはヤバそうな気がしますよね? 細かい説明は余計分からなくなりますので、今から「超ウルトラ・スーパー・ザックリ解説」を行いたいと思いますが、あくまでも個人的な見解ですので、ご活用は自己責任でお願いいたします。 該当する方は「10kW以上設置のFIT・FIP事業者全員」となりますが、 ・設置規模が小さい方 ・屋根上設置の方 以上の方は語弊を恐れずに言えば「あまり気にしなくても良い」と思います。 逆に、 ・地上設置(野立て)の方 ・設置規模が大きい方 この方々は「大いに気にしましょう!」という感じです。 もうお分かりでしょうか? 「規模が小さいか大きいか?」「屋根上設置か地上設置か?」で状況が変わってきます。 その前に、「そもそも委託って何?」のところから説明しなければ全体像が見えてきませんので、こちらと合わせて説明します。 |
何が「委託」に含まれるのか?
| 多分、この記事をご覧の方は「太陽光を設置したけど、定期報告は1度も出したことがない」という方が多いのではないでしょうか? もし上記に該当する方、または「1・2回出したけど今は何もしていない」という方は、 過去ブログ「太陽光発電の年次報告、定期報告来た!どうすればいいの??」をご覧頂いた上で、予備知識としてこちらを見て頂いた方が良いかも知れません。 ☆太陽光発電の年次報告、定期報告来た!どうすればいいの?? https://tsukamoto-re.com/347/ では本題です。 太陽光の設置後(運転開始後)で「委託」として扱われるものは、「保守管理」の部分です。 屋根上設置の方で「保守管理」となりますと世間一般で言われる「定期点検」となりますが、もしこれを「自分で実施している」となりますと「委託先ゼロ」となる訳です。 ただ、屋根上設置の方でも設置規模が50kWを超える「高圧設備」となりますと、事業者様自ら点検とはいかなくなります。 当然、有資格者(主任技術者)の点検が必要となりますので、この場合は「委託先がある」ことになります。 そして、「委託先が発生した場合」は事業者様の監督責任が問われるようになった訳です。 この部分が先の原文に記載されております「認定事業者の監督義務」でございます。 ※具体的な実務内容はここでは割愛します。 当然のことながら、監督義務を履行しているかどうか(委託の実態)については、年1回の定期報告(年次報告)で報告することになる訳ですが、今までと違うのは文言に「認定取消しといった厳格な対応を行う」と明記されていることです。 今までの表現ですと「場合によっては認定取消しもあり得る」でしたが、今回は「厳格な対応」に変わっておりますので、冗談抜きで「委託に該当」する事業者様は、今までのように「何もしていない」は本当の意味で通用しない気がしております。 |
| 以上を踏まえて、 設置規模が50kW未満の「低圧で屋根上設置」の方は、 ご自身で全て管理される場合は「委託先ゼロ」で通すことが出来ます。 なら、同じく「50kW未満の低圧で地上(野立て)設置の方も委託先ゼロで良いのか?」となれば、委託先ゼロで良いことになります。 が、しかしです! 「野立て設置の方は、設置方法の違いがそのままリスクとして加算されている」ということを頭に入れておいた方が良いかも知れません。 ※赤文字の部分は次回(その3)で解説します |
「委託に係る事項」の本質はどこにある?
| 先程のような説明をしますと、 「50kW未満は ”委託先なし” で大丈夫で、50kW以上になると ”委託先あり” となるから・・・ じゃぁ〇〇の場合は ”委託先なし” で行けるのか?」 みたいなご質問をされる方がおられますが、残念ながらこれから先は「抜け道探し」の運営方法では通用しなくなると思っています。 そもそも、「低圧の太陽光は適当な運営が許されて、高圧太陽光は厳格な運営を強いられる」というものではございません。 10kW以上の太陽光発電は規模の大小に関係なく、「電力会社の原発や火力発電所と同列」の位置付けでございます。 という事は、管理・運営方法も「電力会社の原発や火力発電所と同列」までとは行かなくても、 「設計段階での想定発電量を維持できるための管理・運営体制を取っていいますよね?」という前提の下での「委託に係る事項」でございます。 正直、低圧太陽光で何もしていない方は非常に多いですが、高圧太陽光でも主任技術者(キュービクルの点検)以外、何もしていないという方はまあまあおられるのではないでしょうか? 以上より、これからの定期報告(年次報告)は「どのように発電所の維持管理に努めていますか?」という内訳を報告する事が目的と予測しております。 |
定期報告は必要?(その2まとめ)
| 前回投稿(その1)からの「まとめ」となりますが、定期報告は、 ①1年間でどれだけ発電したか? ↓ ↓ ②設備を撤去・処分する際の費用を売電収入から計画的に積立しているか? ↓ ↓ ③どのように発電所の維持管理に努めているか?(内訳) ※「委託に係る事項」の追加 というように流れているかと思います。 ここであらためておさらいします。 定期報告の申請内容が変わってきたのは、当初は申請が必要だった(と思われていた)ものが申請しなくても対応可能になったからであります。 そもそも、定期報告は「誰に報告するのか?」と言えば「制度の運営側(国)」でございます。 では制度の運営側(国)は「申請で得られた情報を何かに活用したかった」から、定期報告のフォーマットを用意したと私は思っており、それが時代によって上記のようにコロコロ変わっていると考えています。 具体的には、 上記①の「1年間でどれだけ発電したか?」の情報が欲しい目的は、おそらく「再エネ賦課金」の算定に活用したかったからだと思います。 ところが、いざ制度が始まりますと誰も報告しないわけです。 まさに、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」マインドでございます。 では、どのように再エネ賦課金を算出しているのかと言えば、各電力会社から情報をもらっていると思われます。というより、間違いなくもらっている筈です。 売電を支払っている電力会社に「年間にどれだけ払ったか?」を聞けば一番確実ですよね? そして制度を運営して数年が経ちますと、今度は野立て太陽光の自然災害による被害がクローズアップされてきました。 自然災害で「復旧の目処が立たない太陽光発電」はもちろんのこと、仮に20年が経過して固定買取りが終了した場合に、「撤去・処分費がないからそのまま放置が大量発生」したら、国としても「ヤバい」と思った筈です。 そこで出てきたのが、上記②の「設備を撤去・処分する際の費用を売電収入から計画的に積立しているか?」だと思います。 これも圧倒的に誰も報告しないわけです。 で、積立できているか?の情報が一向に集まらないものですから、「売電開始の11年目以降より強制徴収となった」と考える方が自然ではないでしょうか? お分かりでしょうか? 今までは「定期報告を無視」していても、国が対策を立てられる状況だった事を。 では、上記③の「どのように発電所の維持管理に努めているか?(内訳)」の目的はと言えば、太陽光ガイドラインに則った保守・管理を「具体的に実行している者は誰か?」という所に焦点が当たっているような気がしております。 では、これも今までの例に沿って「誰も報告しない」となった場合、国はどの様な対策が取れるかをお考え頂きたいのですが、、、これ、結論から申しますと今までの様な対策は立てられないと思いますが、どうでしょうか? 今回は、「発電事業者様からの情報がなければ実態の把握ができない」初めてのパターンでございます。 したがって、もし国側がここの部分を「本気で取り組む」というスタンスであれば、 今回ばかりは →発電事業者様からの申告がない →情報が得られない →事業者としての義務を果たしていない →認定取り消しの対象者リストに入る となるような気がしております。 次回は、この制度での「設備の規模でリスクが変わる(と思われる)具体的な話」をしたいと思います。 ======================== 愛知県の瀬戸市と尾張旭市、長久手市を中心に太陽光発電・蓄電池の販売・施工・メンテナンスを行っております。 「最近、売電収入が減ったような気がする・・・」とお感じの時は、「パワコン」や「太陽光パネル」の不具合が起きているかも! 当社は不具合対応の多数実績がございます。調査が必要かどうかの判断もお問い合わせ頂ければすぐに分かります! まずはお気軽にお問い合わせくださいませ! |